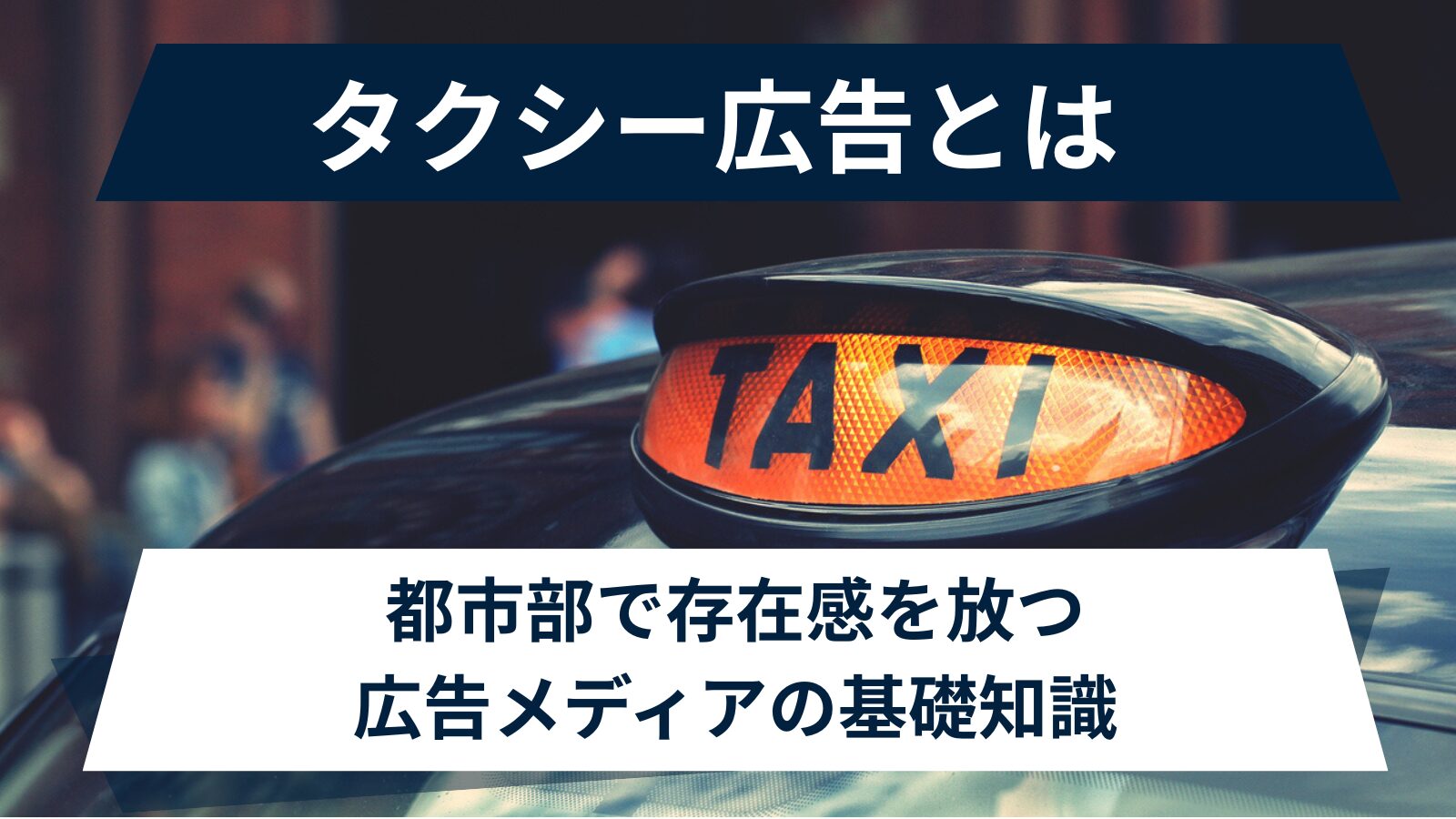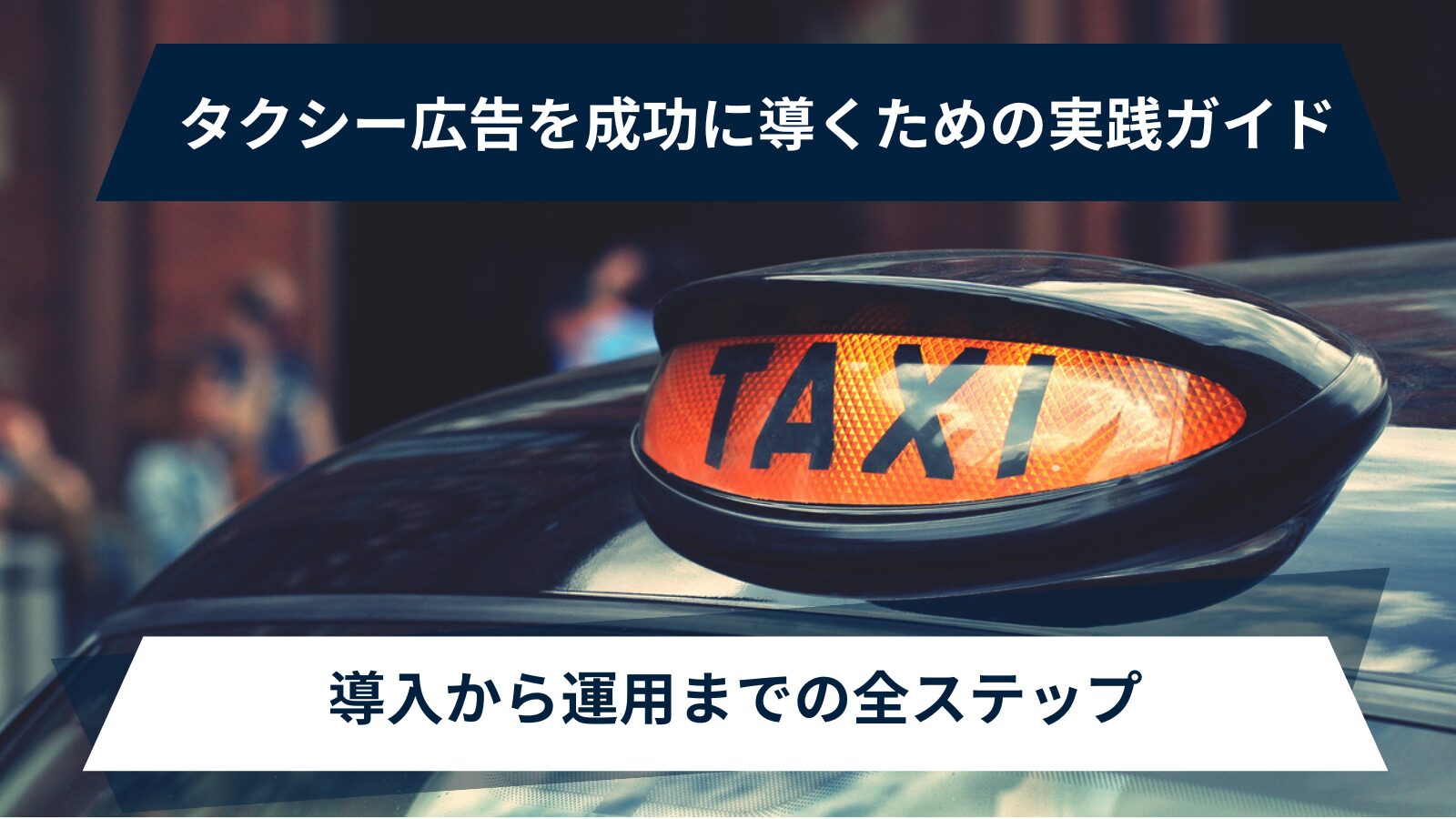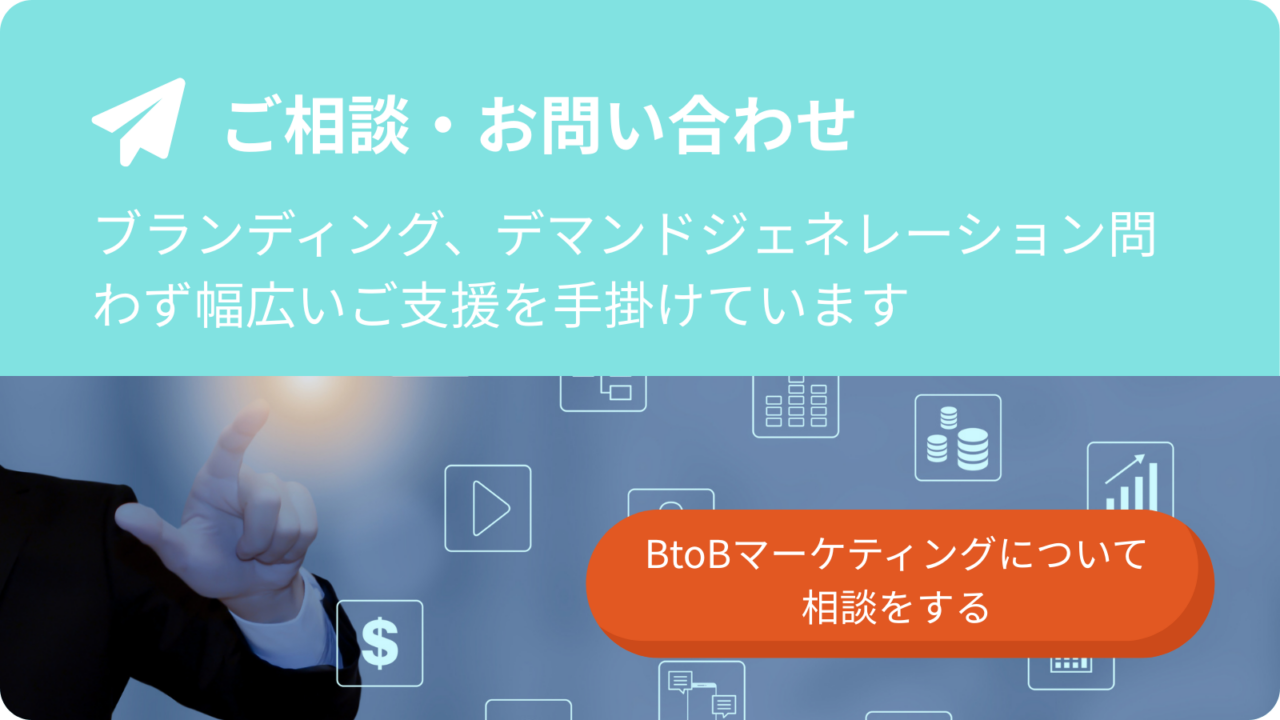タクシー広告 | BtoB企業が注目する理由と効果的な活用法

コロナ禍を経て注目を集めるタクシー広告市場
新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着きを見せ、人々の移動が活発化している中で、タクシー広告が急速な成長を遂げています。株式会社CARTA HOLDINGSが2021年に実施した「デジタルサイネージ広告市場調査」によると、2020年に約25億円だったタクシー広告の市場規模は、2022年には45億円、2025年には60億円まで成長すると予想されています。
タクシー広告とは、タクシーの座席に設置されたタブレットを通じて配信される動画広告のことで、「タクシーサイネージ」とも呼ばれています。運転席または助手席の後頭部に設置されたタブレットを通じて、後部座席の乗客に動画コンテンツを視聴してもらう仕組みです。
この成長の背景には、コロナ禍で一時的に減少したタクシー利用が回復し、むしろ従来以上に利用者が増加していることがあります。感染リスクを避けるため公共交通機関を避け、プライベート空間であるタクシーを選ぶビジネスパーソンが増えたことで、タクシー広告のリーチ力も向上しています。
特に注目すべきは、BtoB企業によるタクシー広告への出稿が増加していることです。これまでテレビCMやWeb広告が主流だった企業向けマーケティングにおいて、なぜタクシー広告が選ばれるようになっているのでしょうか。
編集部コメント: コロナ禍の影響で一時的に市場が縮小したタクシー広告ですが、現在は急速な回復を見せています。特に企業の移動が活発化し、ビジネス利用が増えていることが市場拡大の要因となっています。
BtoB企業がタクシー広告を選ぶ3つの理由
1. 経営層・意思決定層への効果的なリーチ
タクシー広告最大の魅力は、企業の経営層や意思決定層に効果的にアプローチできることです。一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会が実施した「タクシーに関するアンケート調査」では、会社経営者の約半数以上が月に10回以上タクシーを利用すると回答しています。
これは電車やバスなどの公共交通機関と比較して運賃は高いものの、移動効率や快適性を重視する経済的余裕のある層がタクシーを頻繁に利用していることを示しています。BtoB企業にとって、商談や契約の最終決定権を持つこれらの層にダイレクトにアプローチできることは、従来の広告手法では実現困難な大きなメリットです。
2. 集中して視聴してもらえる環境
テレビCMやYouTube広告では、視聴者が広告をスキップしたり、他のことに注意を向けたりするリスクがあります。一方、タクシー広告では、1回の利用あたりの平均乗車時間が18分(株式会社IRIS調べ)と比較的長く、乗客は限られた空間で動画に集中しやすい環境にあります。
さらに、経営層や富裕層は月に複数回タクシーを利用する傾向があるため、同じ広告を繰り返し視聴してもらうことで、ブランドの認知度向上や記憶定着に大きく貢献します。このような反復効果は、BtoB企業の長期的な営業戦略において非常に重要な要素です。
3. 精密なターゲティング機能
現代のタクシー広告では、タブレットに内蔵された顔認識機能を活用して、乗客の年齢や性別を判別し、配信する広告を出し分けることが可能です。また、配信の時間帯や曜日、地域を限定することで、狙ったターゲットのみに効率的に配信でき、広告予算の無駄を防ぐことができます。
例えば、平日の朝の時間帯に都心部を走行するタクシーで、40代以上の男性に対してのみBtoB向けソリューションの広告を配信するといった、細かなセグメンテーションが実現できます。
編集部コメント: 特に注目すべきは、タクシーという移動手段自体がすでに一種のターゲティングになっていることです。タクシーを日常的に利用する層は限定されており、その多くが企業の意思決定に関わるポジションにいる方々です。
タクシー広告の課題と対策
初期投資の高さという課題
タクシー広告の最も大きな課題は、初期投資の高さです。リスティング広告やディスプレイ広告などの運用型Web広告が数十円から数百円単位で開始できるのに対し、タクシー広告は1週間の配信で最低でも数十万円から、首都圏では200万円から700万円程度の投資が必要です。
特に乗車直後の1本目に流れる広告は視聴率が高い反面、非常に高額になる傾向があります。この課題に対しては、2本目以降に流れるプランや、ランダム配信プラン、配信時期や時間を限定したプランを活用することで、コストを抑制しながら効果的な配信が可能です。
リーチ数の限界とその対策
タクシーは他の交通機関と比較して利用者数が限られるため、大規模なマス向け広告としては不向きです。特に20歳未満の若年層のタクシー利用は非常に限られており、若年層をターゲットとするBtoC商材には適していません。
しかし、BtoB企業にとってこの特性は必ずしもデメリットではありません。質の高いターゲット層に確実にリーチできることを重視し、量よりも質を追求する戦略として活用することで、この課題を強みに転換できます。
編集部コメント: タクシー広告の高い初期投資は確かに課題ですが、獲得できる顧客の質の高さを考えると、ROI(投資対効果)の観点では十分に見合う投資といえるでしょう。
効果的なタクシー広告制作のポイント
ターゲットの課題を明確化する
タクシー広告を制作する際は、まずターゲットが抱える課題を明確にすることが重要です。タクシーに乗車する層は比較的富裕層が多いため、一般的な広告でよく見られる「安い」という訴求はあまり効果的ではありません。
むしろタクシーを利用していることから、ターゲットの課題は金額よりも時間や手間に関する問題であることが多いです。「時間の節約になる」「手軽で効率的」「業務の生産性向上」といった価値提案の方が、より響きやすい傾向があります。
飽きさせない工夫を取り入れる
インストリーム広告とは異なり、タクシー広告は途中でスキップできません。この特性を活かすため、スマートフォンや外の景色に注意を向けられないよう、視聴者を惹きつける工夫が必要です。
実写であればストーリー性を持たせたドラマ形式、アニメーションや静止画の組み合わせであれば大きなテロップや効果音を多用することが有効です。タクシーという没入しやすい環境と、スマートフォンより大きな画面を活かし、通常のネット広告以上にクリエイティブにこだわることが重要です。
制作費用と外注の活用
30秒程度の動画広告制作費用は、アニメーション・実写ともに一般的には100万円程度が相場ですが、動画制作プラットフォームを活用することで30万円程度から制作依頼が可能です。限られた時間の中で効果的にメッセージを伝えるため、プロの制作会社との連携は重要な選択肢の一つです。
編集部コメント: タクシー広告の制作では、限られた時間内でいかに印象に残るメッセージを伝えられるかが勝負です。ターゲットの特性を理解した上で、適切なクリエイティブ戦略を立てることが成功の鍵となります。
まとめ:意思決定層へのアプローチを実現するタクシー広告
タクシー広告市場は、コロナ禍を経て急速な回復と成長を続けており、2025年には60億円規模に達すると予想されています。この成長の背景には、BtoB企業による積極的な活用があり、その理由は明確です。
第一に、企業の経営層や意思決定層に効果的にリーチできること。第二に、限られた空間で集中して視聴してもらえる環境があること。第三に、精密なターゲティング機能により、効率的な広告配信が可能なことです。
一方で、初期投資の高さやリーチ数の限界といった課題も存在しますが、これらは適切な配信戦略や予算配分により対処可能です。重要なのは、タクシー広告を単なる広告手法として捉えるのではなく、質の高いターゲット層との接点を創出する戦略的なマーケティングツールとして位置づけることです。
効果的なタクシー広告制作には、ターゲットの課題を明確化し、飽きさせない工夫を取り入れることが欠かせません。また、専門的な制作会社との連携により、限られた時間内で最大限のインパクトを生み出すことが可能になります。
法人営業に課題を抱える企業や、経営層へのアプローチに苦戦している企業にとって、タクシー広告は従来のマーケティング手法では届かない層にアプローチできる貴重な機会を提供します。市場の成長とともに、BtoB企業のマーケティング戦略における重要性は今後さらに高まっていくでしょう。
編集部まとめ: タクシー広告は、デジタル化が進む現代において、リアルな接点を通じて意思決定層にアプローチできる希少な広告媒体です。初期投資は決して安くありませんが、獲得できる顧客の質とその後のビジネスインパクトを考えると、BtoB企業にとって検討すべき重要な選択肢の一つといえるでしょう。今後も市場の成長とともに、より効果的な活用方法が開発されることが期待されます。