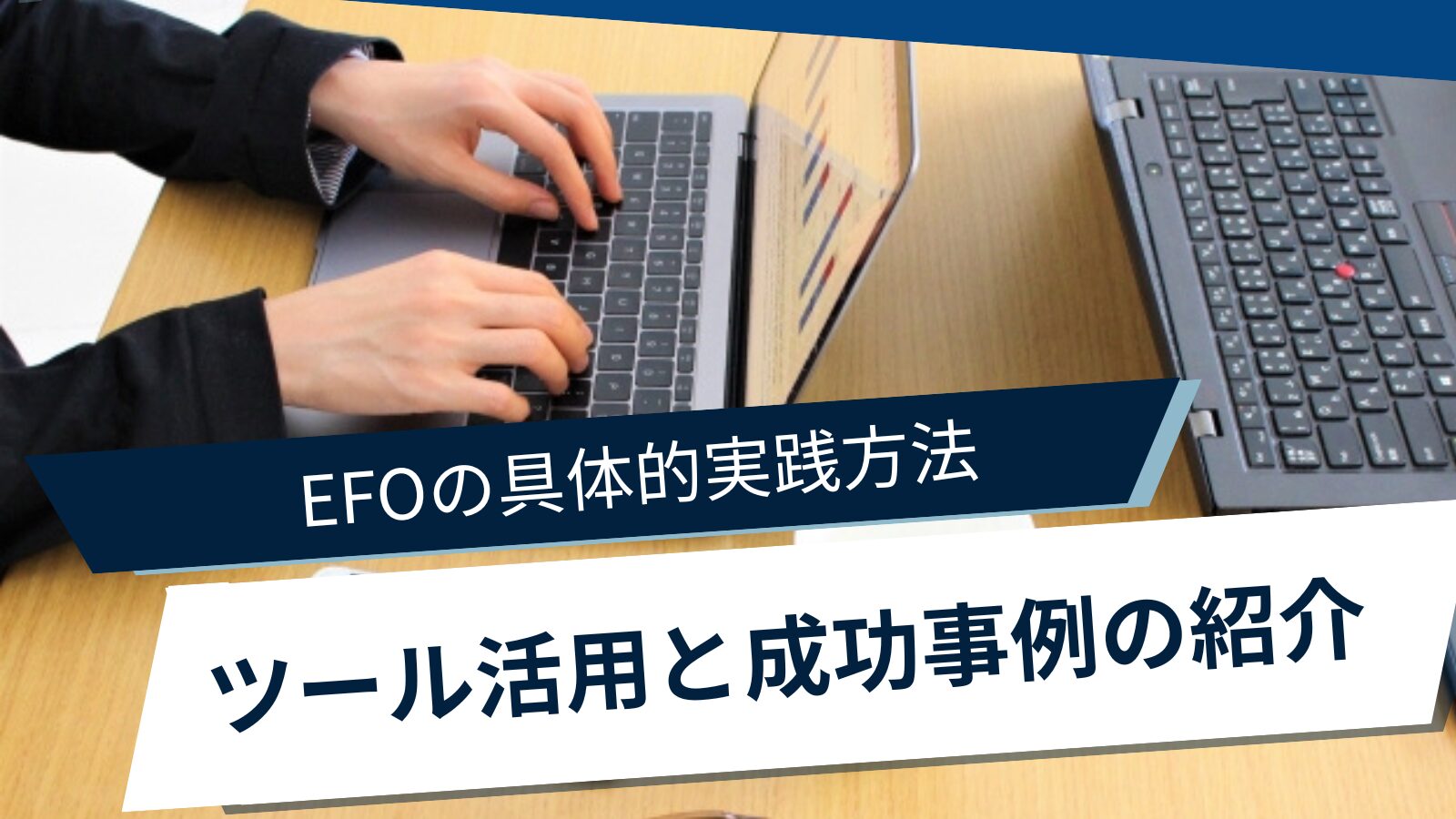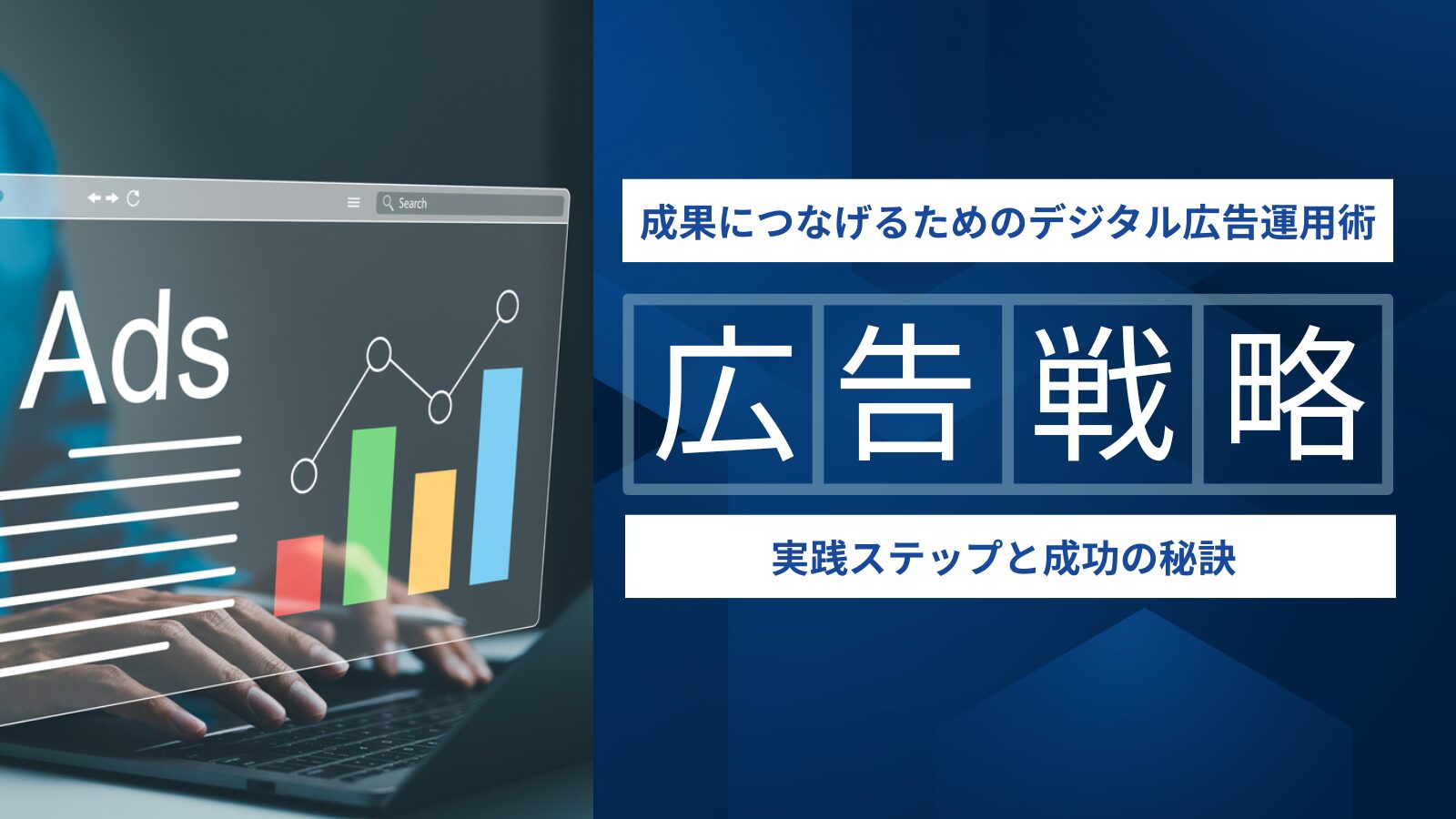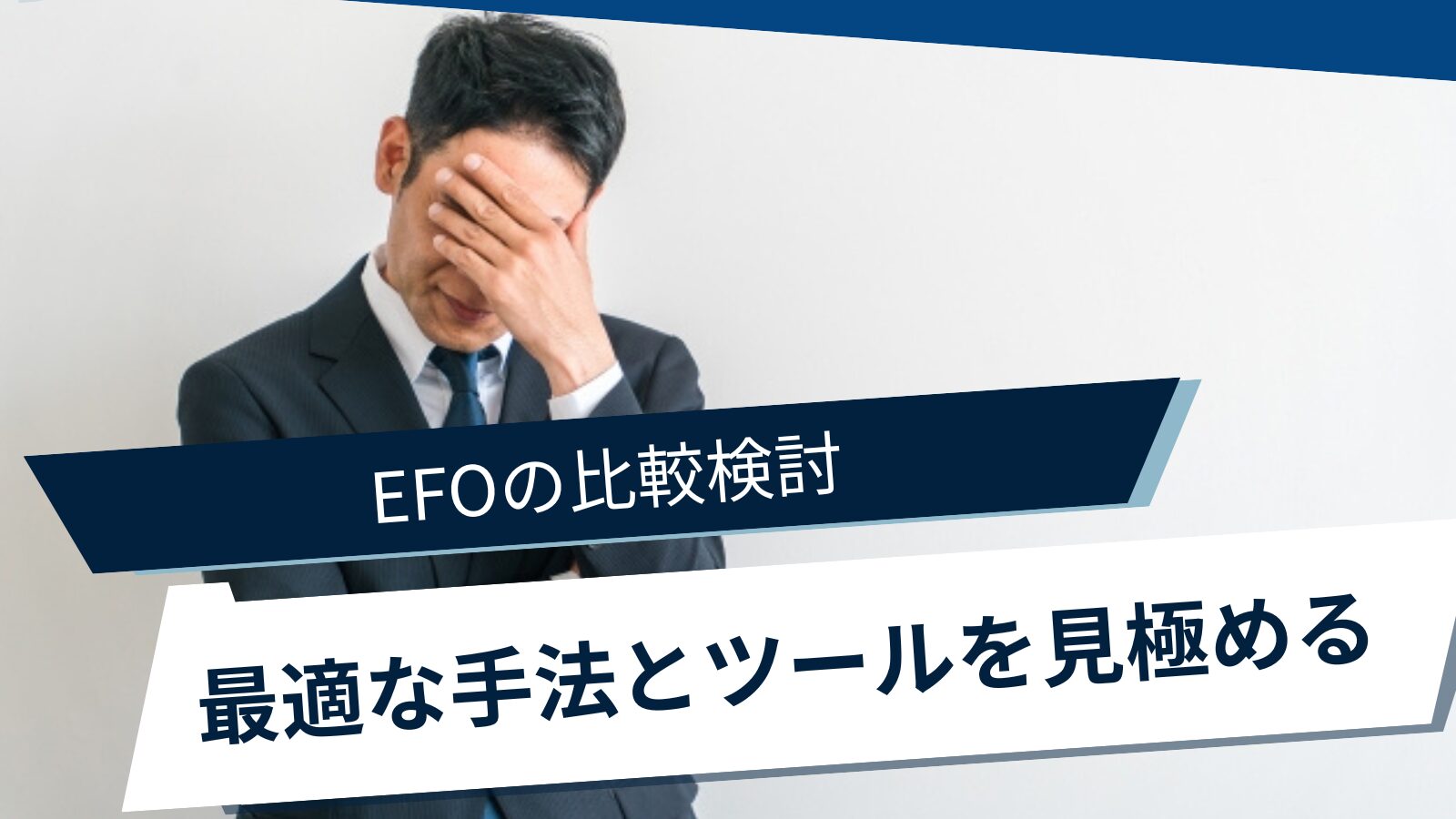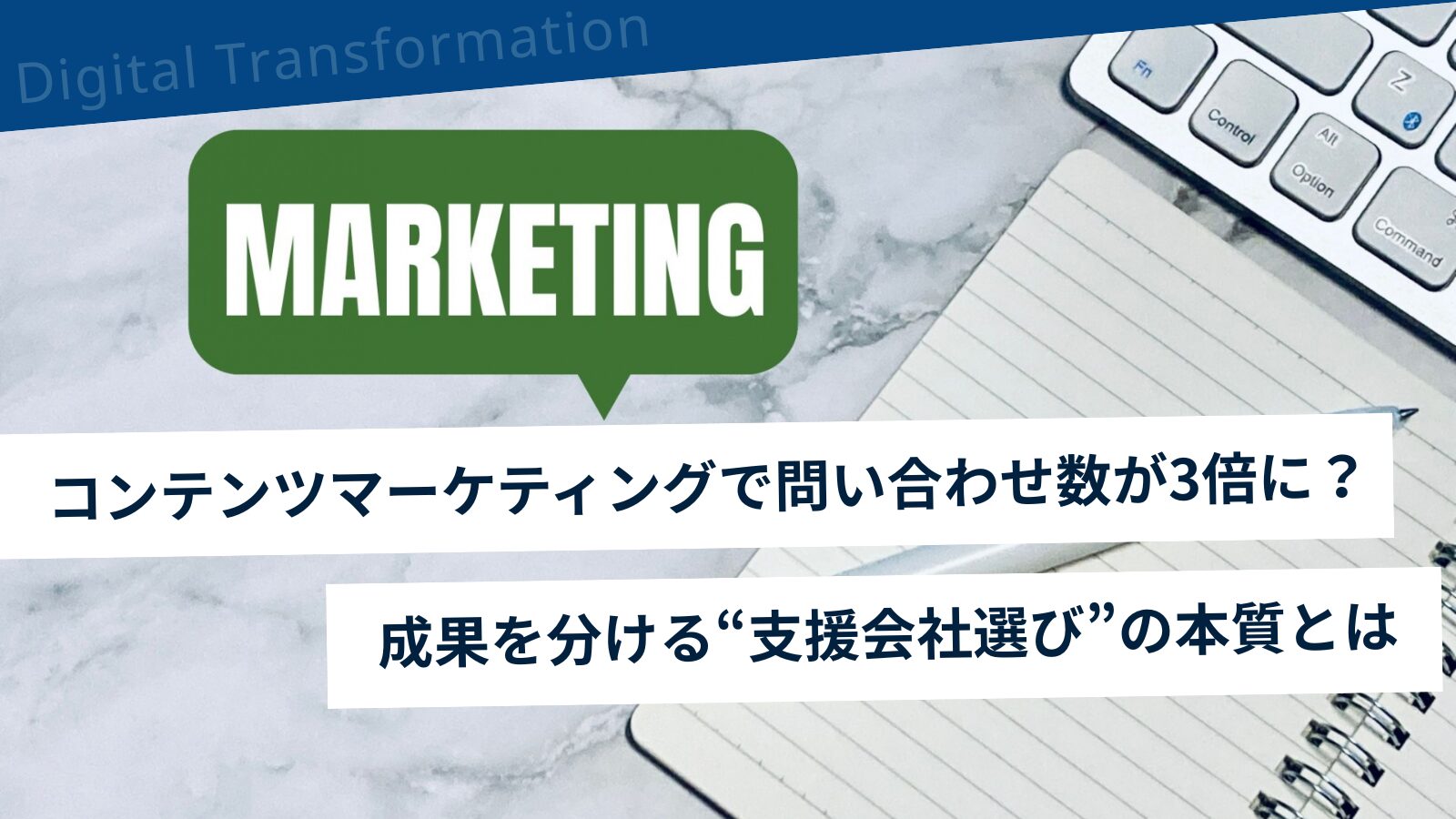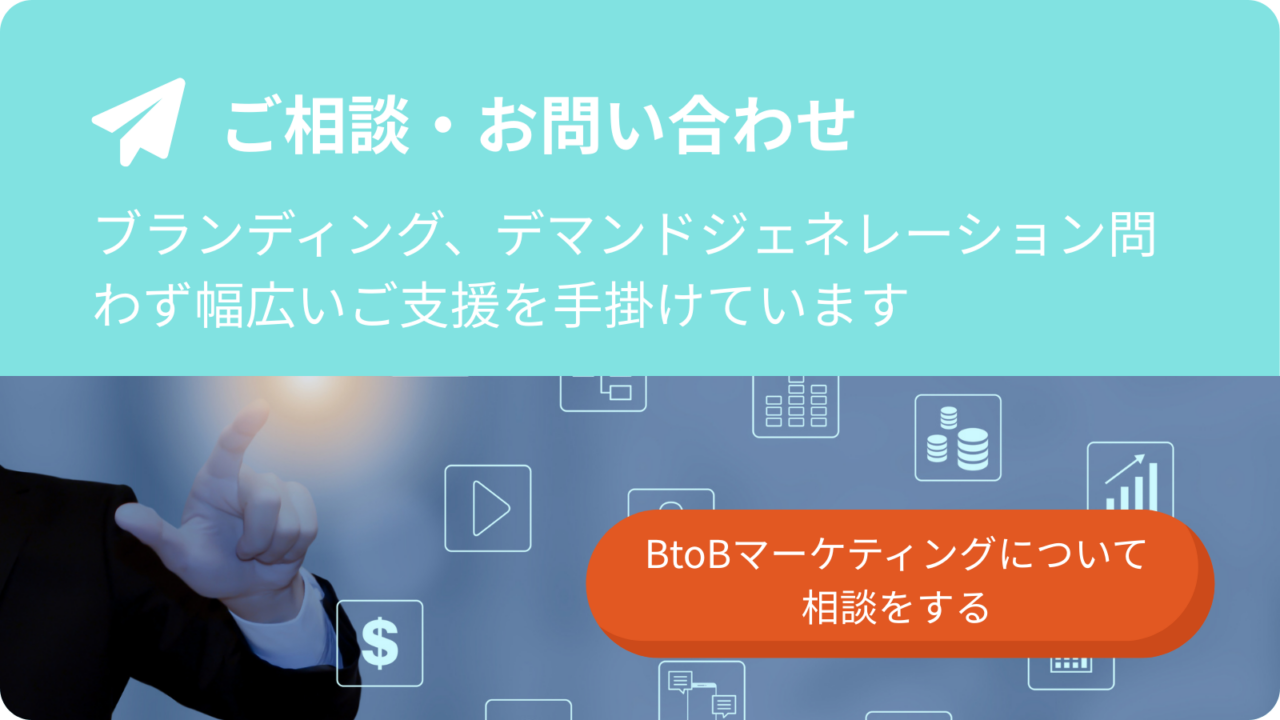リニューアル後に「成果が出ない」BtoB企業がやるべきこと
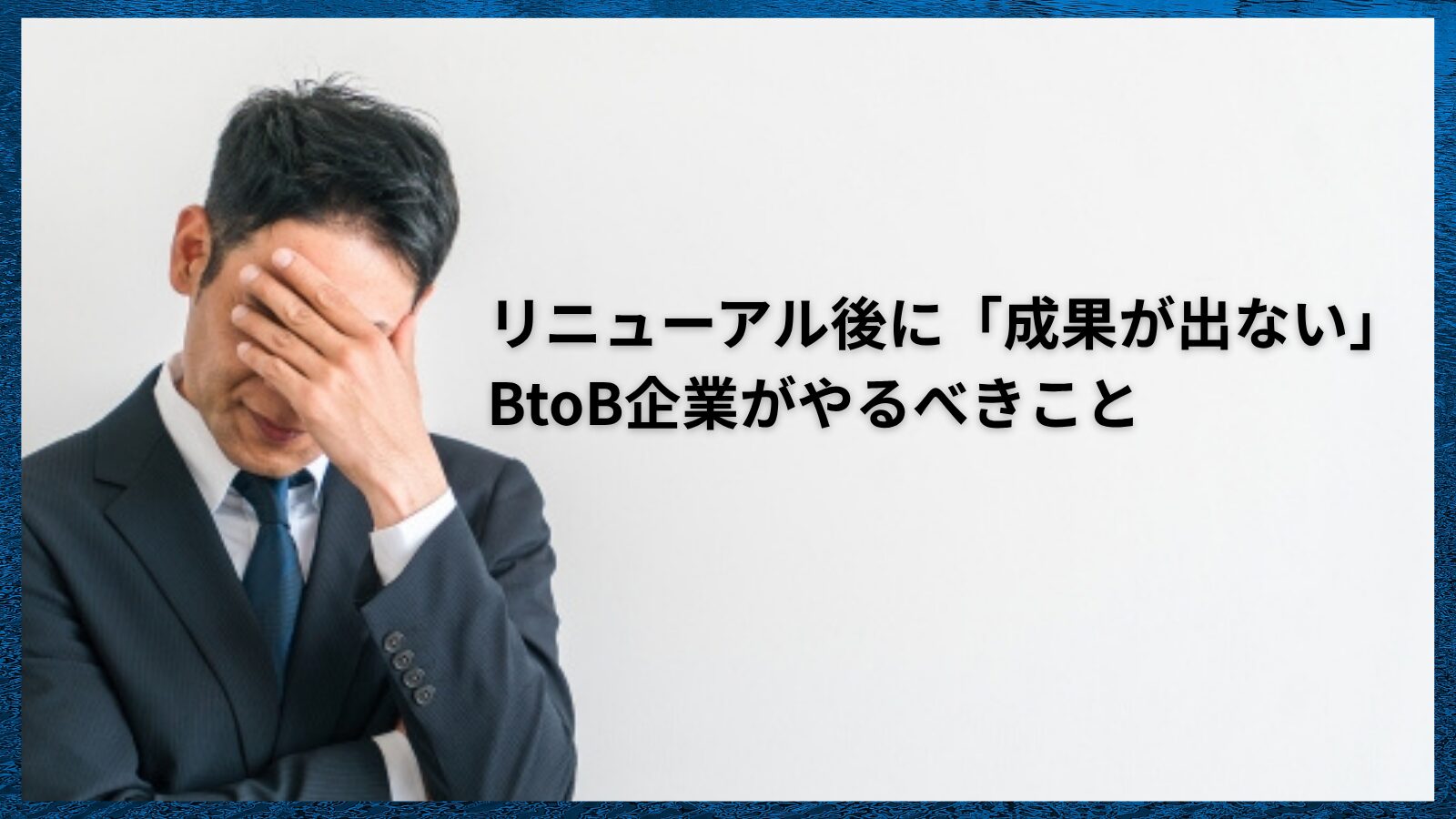
なぜリニューアル後に成果が出ないのか?
「Webサイトをリニューアルしたのに問い合わせが増えない」「アクセスは増えたのに商談につながらない」──BtoB企業の担当者から、このような課題をよく耳にします。
社内稟議を通し、多くの時間と予算をかけて実施したWebリニューアル。それにもかかわらず“見える成果”が出ていない場合、どこかに構造的な問題があると捉えるべきです。これは偶然ではなく、再設計によって改善できる要素が潜んでいる可能性が高いのです。
BtoBのWebサイトが果たすべき役割は、ビジュアルの刷新にとどまらず、商談や受注といったビジネス成果を後押しすることにあります。つまり、問い合わせ件数、資料請求、セミナー申し込みといった“行動”を引き出せていなければ、本来の目的を達成しているとは言えません。
成果が出ない原因の多くは、サイト公開前の設計段階にあります。目的やターゲット像が曖昧なままプロジェクトが進み、最終的に何を成果指標とするのかが曖昧なまま公開に至ってしまう。また、営業部門やインサイドセールスとの連携が設計されておらず、せっかくのコンテンツが後工程に十分に活かされないといったケースも散見されます。
ペルソナ設計の不備がコンテンツの無力化を招く
Webサイトにおけるペルソナ設計は、誰に対して何を伝えるべきかを明確にする上で極めて重要な要素です。BtoBの場合、想定されるユーザーは経営層、事業部門長、マーケティング担当者、情報システム部門など多岐にわたります。
たとえば、経営層は「コスト削減」や「ROI」を重視しますが、現場担当者は「操作性」や「業務改善」の具体策を知りたがります。誰に向けた情報なのかが曖昧だと、メッセージがぼやけ、結果として、誰の意思決定にも影響を与えることができません。ペルソナごとに課題や情報ニーズを整理し、それぞれに適した導線やコンテンツを設計することが、成果への第一歩です。
インサイドセールスと連携した仕組みの設計
Webサイトで獲得したリードを、商談へと育てるにはインサイドセールス(IS)の存在が不可欠です。しかし、IS部門との連携が設計されていないWebは、せっかくの訪問者や資料ダウンロードユーザーを“放置”してしまうことになりがちです。
コンテンツは、単に読ませるだけでは意味がありません。資料ダウンロード後にインサイドセールスがどのようなタイミングでアプローチするか、メールによるナーチャリングと架電の役割分担、スクリプトに活用する情報の取得源など、具体的なオペレーションを前提としたWeb設計ができていないと、成果にはつながりません。
また、ISが営業にトスアップしやすいよう、資料ダウンロード時の行動データやセグメント情報を取得・分析できる仕組みも重要です。MA(マーケティングオートメーション)との連携によって、IS部門が価値あるリードを見極めやすくなる環境整備が求められます。
LPO(ランディングページ最適化)の観点が欠けていないか
広告、メール、SNSからの流入先として設計されるランディングページ(LP)は、1ページ内でユーザーを適切に動かすことを目的とします。ここでは、明確なメッセージ、課題共感、解決策の提示、CTA(行動喚起)の配置といった一連の流れを意識した構成が不可欠です。
ところが、実際には製品情報をそのまま掲載しただけのページや、ページ内導線が弱く直帰率が高いLPも散見されます。ユーザーの目的とLPの情報構造が一致していなければ、離脱を避けることはできません。
LPOの改善では、ファーストビューの訴求見直し、フォームの簡略化、CTAボタンの視認性向上、スマートフォン最適化といった細かな施策が、成果に直結します。Webリニューアルにおいても、流入元との整合性とユーザー行動の予測に基づいたLP設計が欠かせません。
SEO対策の設計と継続運用の重要性
Webリニューアル後に「アクセスが増えない」と感じている企業は、SEO設計が不十分な場合が多くあります。検索エンジンからの流入を獲得するには、ターゲットユーザーの検索意図に合わせたページ設計が求められます。
単なるキーワードの羅列ではなく、「業務課題をいかに解決するか」という観点でのコンテンツが評価される今、質と構造を兼ね備えたページであることが重要です。タイトルタグ、ディスクリプション、Hタグ、内部リンク、構造化データなど、細部まで意識した設計が、リニューアル成功の分水嶺になります。
また、公開後もサーチコンソールや検索順位ツールなどを活用し、検索クエリの変化やページ別の流入傾向を追いながら、継続的に改善を図る姿勢が求められます。SEOは“施策”ではなく、“運用”として取り組む必要があります。

Googleアナリティクスとヒートマップによる改善PDCA
Webサイト改善の意思決定には、定量データと定性データの両方が不可欠です。Googleアナリティクスでは、PVや滞在時間、離脱率、コンバージョン率といった指標を通じて、ユーザーの行動傾向を把握できます。
一方で、ヒートマップツールを活用すれば、ページ上のどこに注目が集まっているか、どこでスクロールが止まっているか、クリックされていないボタンはどこかといった視覚的な分析が可能になります。
これらのツールを用いて現状のボトルネックを特定し、仮説を立て、優先度の高い改善から着手する。このPDCAサイクルを継続的に回すことが、成果につながるWeb運用には不可欠です。
営業と連動したWeb活用が成果を生む
Webリニューアルを外部に依頼する際、制作会社とマーケティング支援会社の違いを認識することが重要です。制作会社はビジュアルや構造の整理に強みを持つ一方、KPI設計やインサイドセールス連携、広告・SEO・ナーチャリングといった施策設計にはノウハウが及ばないケースも多く見られます。
一方で、マーケティング支援会社は、事業成長や営業成果を見据えた“戦略型のWeb活用”を前提に支援を行います。コンテンツの構成だけでなく、流入設計・LPO・CTA設計・営業資料との統一・数値改善のPDCAにまで対応できるパートナーを選ぶことで、Webは単なる「顔」から「成果装置」へと進化します。
まとめ:Webリニューアルは成果創出の“起点”である
BtoB企業にとってのWebサイトは、単なる会社案内ではなく、リード獲得・ナーチャリング・営業支援・ブランディングまでを担う戦略的な資産です。リニューアルはあくまで出発点であり、そこからいかに改善を重ね、顧客との接点を最適化し、営業と連携して成果を上げていくかが問われます。
そのためには、ペルソナの再定義、インサイドセールスとの連携、LPの最適化、SEOの地道な改善、データ分析に基づいたPDCA運用、そして何より「成果を共に考え、支援できるパートナー選び」が欠かせません。
貴社のWebサイトが次の商談を生み出す起点となるよう、今一度その価値を見直してみてはいかがでしょうか。